片方の鼻詰まりは、
副鼻腔炎・片側性副鼻腔炎
かもしれません
 鼻腔(鼻の穴)の奥には、左右1対ずつに「副鼻腔」という空洞(上顎洞、篩骨洞、前頭洞、蝶形骨洞)が存在します。
鼻腔(鼻の穴)の奥には、左右1対ずつに「副鼻腔」という空洞(上顎洞、篩骨洞、前頭洞、蝶形骨洞)が存在します。
副鼻腔は鼻腔に狭い開口部を通じて繋がっており、ここが炎症や粘膜の腫れによって塞がると、副鼻腔の通りが悪化して膿が蓄積します。それにより発症するのが副鼻腔炎です。
副鼻腔の炎症により頭痛や顔面痛が起こり、膿性の鼻汁や粘膜の腫れによって鼻詰まりや鼻漏が引き起こされます。副鼻腔炎は、急性鼻副鼻腔炎と3カ月以上も症状が長引く慢性鼻副鼻腔炎に分類されます。
副鼻腔炎(蓄のう症)の種類
急性副鼻腔炎
風邪などのウイルス感染によって、その数日後に細菌の二次感染が発生した結果起こるものです。主な症状は膿性鼻漏や鼻詰まりで、副鼻腔に重い炎症が生じると顔面痛や頭痛が生じることもあります。
慢性副鼻腔炎
後鼻漏や鼻詰まりなどの急性副鼻腔炎の症状が3カ月以上持続している状態です。炎症によって粘膜の働きが落ちてしまい、副鼻腔にまで及んだ炎症が治りにくくなるという悪循環に陥りやすい病気です。この状態は、一昔前では『蓄のう症』とされていました。
好酸球性副鼻腔炎
鼻茸や粘り気の強い鼻汁を特徴としたアレルギー反応が関与する副鼻腔炎です。成人の喘息患者に多く見られ、篩骨洞を中心とした炎症、ポリープにより鼻詰まりや嗅覚障害を引き起こすことが多いです。
一般的な副鼻腔炎の治療に加えて、内服ステロイド薬を必要により用いますが、長期にわたるステロイド内服治療は生存率を低下させるとの報告もみられます。手術治療を行った後も再発が多いため、国から指定難病として登録されています。
近年、好酸球性副鼻腔炎に適応のある抗体療法が複数開発されており、ステロイド治療を行わずに症状のコントロールが期待できる様になっております。高額な治療になりますが、使用できる体制にはありますので、必要とされる患者さんがおられればご相談ください。
片側性副鼻腔炎
副鼻腔炎は通常両側に起こりますが、片側のものは特殊なタイプで注意が必要です。 炎症性では、虫歯が原因になる歯性上顎洞炎が有名で、歯科治療とあわせて治療を試みます。
問題なのは副鼻腔真菌症と、腫瘍性病変です。 副鼻腔真菌症は鼻内に真菌塊が観察されたり、副鼻腔内にCTで高いCT値を示す真菌塊が描出されることが特徴です。高齢者で散見されますが、稀に激症型真菌症を呈し、極めて浸潤性の高い炎症を起こすことがあります。
腫瘍性病変には、乳頭腫に注意が必要です。乳頭腫はそれ自体は良性ですが、とくに内反性乳頭腫は悪性化したり、すでに悪性腫瘍を含んでいることがあります。悪性腫瘍の代表的なものは、扁平上皮癌、悪性リンパ腫で、稀に腺様嚢胞癌、横紋筋肉腫、悪性黒色腫などが生じることがあります。悪性腫瘍にあまり特徴的な症状はなく、とくに初期には無症状ですが、鼻閉、鼻出血、頬部腫脹、眼球突出など、がんの進展方向により異なる症状が現れることが知られています。
副鼻腔炎の原因
風邪などのウイルス感染
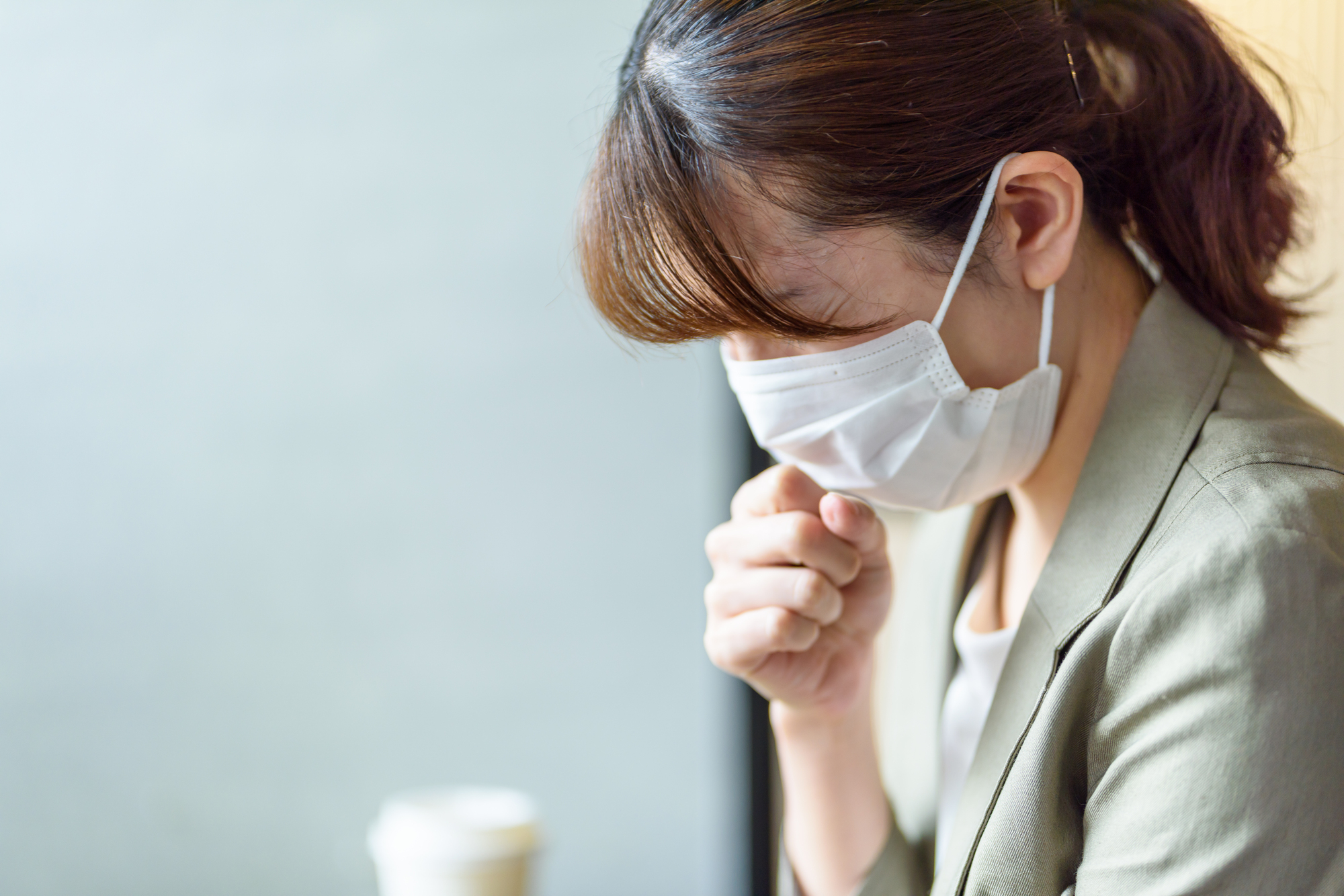 急性鼻副鼻腔炎の多くは、風邪などのウイルス感染が引き金となり、その後に細菌の二次感染が発生することで生じます。
急性鼻副鼻腔炎の多くは、風邪などのウイルス感染が引き金となり、その後に細菌の二次感染が発生することで生じます。
特に、幼児はウイルスによる感染が起こりやすい上に鼻腔も狭いため、鼻詰まりや鼻漏の症状が出やすい傾向にあります。
鼻中隔弯曲症
左右の鼻の穴を仕切る壁を「鼻中隔」と言います。通常、鼻中隔は若干弯曲していますが、その弯曲が強くなると、鼻詰まりが起こりやすくなります。この場合、『鼻中隔矯正術』という手術で鼻詰まりを改善することがあります。
鼻中隔弯曲症を発症すると、鼻腔が炎症したり粘膜が腫れたりすることもあり、副鼻腔炎を引き起こしやすくなります。
真菌
空気中に漂う真菌(カビ)が副鼻腔内に侵入することで、真菌性副鼻腔炎(副鼻腔真菌症)を発症することがあります。この場合は副鼻腔のCT検査などで診断をつけてから、手術による治療を実施します。
副鼻腔炎の症状
副鼻腔炎の症状は下記の通りです。急性副鼻腔炎では、粘り気の強い黄色の鼻水と顔面の痛み、頭痛が主な症状です。一方、慢性副鼻腔炎では、粘り気の強い黄色の鼻水や後鼻漏が見られます。好酸球性副鼻腔炎では、鼻詰まりや嗅覚障害が多く見られます。なお、後鼻漏とは鼻水が喉に落ちる症状で、不快感を伴うのが特徴です。
- 鼻詰まり
- 鼻水、粘り気の強い黄色い鼻水
- 後鼻漏
- 咳や痰が出る
- 顔面の痛み、頭痛
- 嗅覚障害
副鼻腔炎をそのまま放置しておくと…
急性副鼻腔炎が進むと、眼窩内合併症(視力障害)や頭蓋内合併症(髄膜炎)を引き起こすことがあるため、抗菌薬による適切な治療が不可欠です。眼窩内合併症や頭蓋内合併症をきたした場合には、緊急手術が必要です。慢性副鼻腔炎は薬物療法や手術療法で改善することが多いですが、好酸球性副鼻腔炎は手術後も鼻茸が再発しやすいため、診察と治療を続けなくてはなりません。
副鼻腔炎の検査
 副鼻腔炎の際には、中鼻道を中心とした膿性鼻汁がみられたり、後鼻漏が見られることがあり、症状の発症具合や鼻内の視診所見からある程度の推測は可能です。起炎菌の検索や抗生物質の感受性の確認のため、細菌培養を採取します。肉眼所見は内視鏡所見には劣りますので、鼻腔内をくまなく観察する目的で、内視鏡検査を行うこともあります。
副鼻腔炎の際には、中鼻道を中心とした膿性鼻汁がみられたり、後鼻漏が見られることがあり、症状の発症具合や鼻内の視診所見からある程度の推測は可能です。起炎菌の検索や抗生物質の感受性の確認のため、細菌培養を採取します。肉眼所見は内視鏡所見には劣りますので、鼻腔内をくまなく観察する目的で、内視鏡検査を行うこともあります。
こうした検査方法では副鼻腔の内部まで観察することはできません。副鼻腔は骨に囲まれた領域ですから、放射線の力を使って、内部を透視する必要があります。副鼻腔のレントゲン検査も可能ですが、なんとなく副鼻腔が曇って見える、程度の所見しか得られません。
CTでは、水平断(輪切りの状態)だけでなく、他の方向の断面を構成することもでき、とくに前額断は顔が前から順々に切れていく方向で画像を示せますので理解がしやすいと思います。
どこに病変があるのか、骨が破壊される病気ではないか、など、圧倒的に多くの情報を得られますので、治療前の診断のみならず、治療の途中経過や効果判定にお勧めです。
当院のコーンビームCTは被曝量が極めて少なく、放射線被曝の問題はほぼ無視できる程度です。
副鼻腔炎の治療
急性副鼻腔炎では、抗生物質を使用して消炎を図ります。アレルギー性鼻炎の関与が疑われる場合にはアレルギー性鼻炎の治療を併用して行います。
慢性期には、クラリスロマイシンの少量長期投与を中心に、3ヶ月程度治療を継続します。内服治療で反応が乏しく、改善が見られない場合には手術を検討するべきです。
片側性副鼻腔炎の場合、とくに腫瘍性病変が疑われる際には、当院での検査のみでなく、組織採取やMRIなども必要になります。手術治療を含め、提携医療機関と連携いたします。
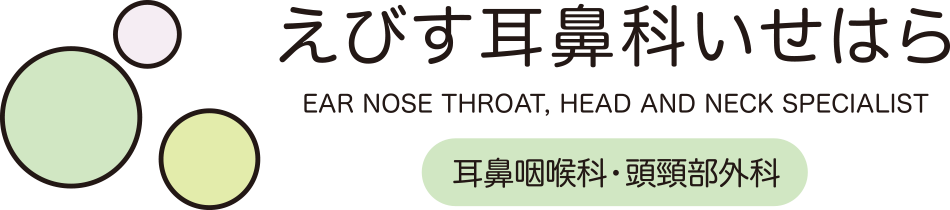





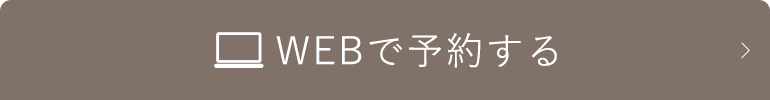

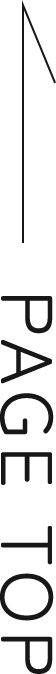
 花粉やハウスダストなどによって起こる鼻炎です。鼻の粘膜が腫れている場合、鼻詰まりなどの症状が起こりやすく、細菌性副鼻腔炎の症状も悪化しやすくなります。
花粉やハウスダストなどによって起こる鼻炎です。鼻の粘膜が腫れている場合、鼻詰まりなどの症状が起こりやすく、細菌性副鼻腔炎の症状も悪化しやすくなります。