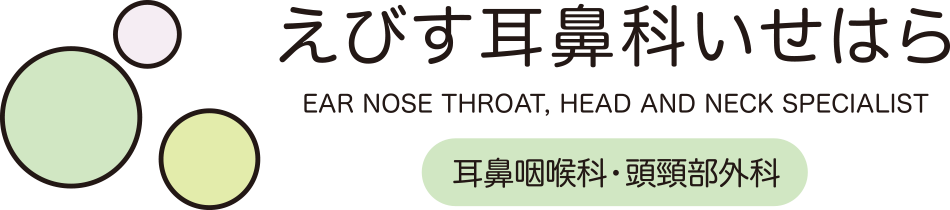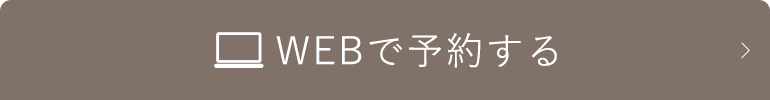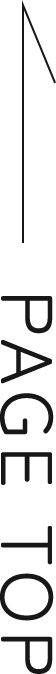補聴器相談について

補聴器は会話が聞き取りにくくなった時にはっきりと聞くための管理医療機器です。厚生労働省が指定する講習会を修了した補聴器適合判定医や、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定の補聴器相談医の診察のもとで必要性を判断することが勧められています。院長はこの両方の資格を有しています。耳の状態と聴力を適切に診断・評価した上で、患者さんと相談しながら、快適な聞こえにつなげられるように対応いたします。
補聴器相談では、まず耳や鼓膜の状態、聴力検査、ことばの聞き取りの検査から、治療や処置が必要な疾患がないかを確かめます。外耳炎や中耳炎など、治療が必要であればそれらの治療を優先した上で、補聴器による聞こえの改善が可能かどうかを判断します。
補聴器で聞こえ具合を改善できると判断された場合は、認定補聴器専門店の協力のもと、患者さんの日常生活の過ごし方などをお聞きしてからそれぞれに合ったものを選択していきます。試用の結果をもとに調整を行い、快適に聞こえることが確認できましたら購入をご検討いただきます。試用機器が合わない場合は、別の機器を貸し出し、その都度調整を行います。
補聴器相談は毎週火曜日の午後の事前予約制となります。ご希望の場合は、まずは一般外来へ受診し、診察・検査をうけてください。
診察をして見た目の異常がないことを確認、聴力検査、語音聴力検査を行った上で補聴器のお話し、という流れにする予定です。
難聴について
音が聞こえにくい状態を難聴といい、その重症度には個人差があります。障害部位によって伝音難聴、感音難聴、混合性難聴に分類されます。聴力検査では、軽度から高度な難聴まで診断することが可能です。難聴がわかるきっかけによっても診断をある程度絞り込むことができます。問診と聴力検査の結果、診察所見を総合して診断治療にすすみます。
難聴に対する受け止め方は、患者さんのライフスタイルや職業などによって大きく異なります。聞こえづらさの感じ方も1人ひとり大きく異なりますので、難聴の度合いに関わらず、聞こえにくいと感じましたらお気軽に当院までご相談ください。
補聴器について
補聴器は、加齢による難聴によって、日常生活に支障をきたしている場合に用いられる医療機器です。安全に生活するために目安となる聴力は定められていますが、特定の聴力になったからといって必ず補聴器を使わなければならないわけではありません。聞こえにくさで悩んでいる時に使用するものと捉えていただければと思います。
補聴器の選び方

医療技術の進歩は早く、様々な機能や形状、大きさの補聴器が日々登場しています。オーダーメイド製品や多くの機能が搭載されているハイスペックモデルのように、高価な補聴器も存在しますが、高いからといって必ずしもご自身に合うとは限りません。オーバースペックになって使いこなせなかったり、小さすぎて操作しにくかったり、なくしてしまったりといった問題が生じることも少なくありません。オーダーメイドで作成した場合でも、素材感や使用感が好みに合わなければ快適に使用することは難しいでしょう。
難聴の程度や低下している周波数は1人ひとり大きく異なります。耳障りだと感じる音も個人差が大きいです。複数人での会話、駅構内などの騒がしい場所、電話での会話、テレビの音など、同じ音でも環境やシチュエーションによって聞こえ方は大きく変わります。加えて、補聴器は装着してすぐに聞こえが良くなるわけではありません。色々な環境やシチュエーションで使用し、感じたことを患者さんからお聞きした上で調整を繰り返し、聞こえ方や機能、素材感、見た目、耳にフィットしているかなど、患者さんご自身の好みやライフスタイルに合った補聴器が完成されます。使用しながら気になることを具体的に、かつ細かくお伝えください。
その方のための調整が行われていない補聴器では、音がうるさく耳障りに感じられたり、うまく言葉が聞き取れない可能性があります。集音器も同様で、集音器は低音から高音まで全ての音を大きくするので、聞こえにくい音をある程度大きくできても、よく聞こえる音も一緒に大きくなってかき消されてしまい、聞こえの改善に繋がらないことも多いです。適切な補聴器を作るには、1人ひとりに合った補聴器の選択ときめ細やかなメンテナンスが必要です。
補聴器購入時の公費負担制度と医療費控除
聴力検査を受けていただいた結果、難聴の重症度が身体障害者の認定基準に当てはまった場合、公費負担制度の対象となります。なお、身体障害者手帳の発行と、補聴器の購入費用の支給申請は、それぞれ別に行わなくてはなりません。自己負担額は収入に応じて定められています。
当院では、聴力検査の結果が身体障害者の認定基準に当てはまる方に対して、申請についてのご説明も行っています。また、申請に必要な診断書の作成にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
補聴器相談医の診断のもと、認定補聴器専門店(認定補聴器技能者が在籍しています)から購入した補聴器は、確定申告をすれば医療費控除を受けることができます。こちらもお気軽にご相談ください。
補聴器外来診察の流れ
1一般外来での診療

問診と診察、聴力検査を行い診断します。
補聴器の適用がある場合は、以下の流れへ進むことを提案します。
2ご相談
診断結果について説明した上で、聞こえに関するお悩みや、日常生活に支障をきたしていないかなどについてお伺いします。
お悩みをお聞きしてから補聴器についての説明を行い、認定補聴器専門店の協力のもと、実際に装用した状態で視聴し、使用感を確認していただきます。その際には、購入費用についても分かりやすくご説明します。
3補聴器の貸し出し
装用や使用感が合うと感じた補聴器がありましたら、貸し出しへ進んでいただきます。ある程度の期間使用していただき、再診時に気になった点などについてお聞きしてから、必要に応じて補聴器を調整します。
様々な環境での聞こえ具合によって、調整を何度か繰り返し、より快適に音を聞こえるようにした上で、購入をご検討いただきます。ご相談の上での補聴器選択または貸し出しを行う際には、必ず購入金額についての説明も行います。
4アフターケア
補聴器は生活環境やその時々のシチュエーションによって、聞こえ方が大きく変わる可能性もあります。そのため、購入していただいた後でも定期的な微調整を行い、快適な聞こえを長く維持することが重要です。
また、補聴器は精密機器ですので、掃除やメンテナンスも重要になります。当院では、聞こえ方の微調整や定期的な掃除、点検などにも丁寧に対応しております。