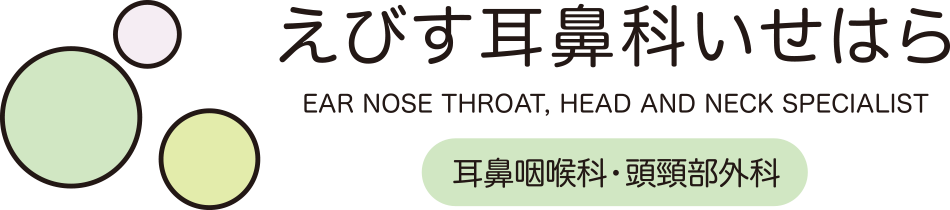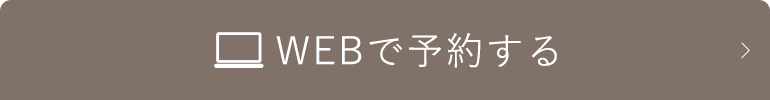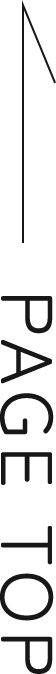めまいって耳からくるの?
 めまいを感じると、真っ先に脳の異常を疑う方も多いかもしれません。実際にはめまいの原因の多くは耳といわれますが、耳性めまいと中枢性めまいを比べると緊急性や疾患としての重要度は中枢性めまいの方が圧倒的に高いので、その感覚は正しいと思います。
めまいを感じると、真っ先に脳の異常を疑う方も多いかもしれません。実際にはめまいの原因の多くは耳といわれますが、耳性めまいと中枢性めまいを比べると緊急性や疾患としての重要度は中枢性めまいの方が圧倒的に高いので、その感覚は正しいと思います。
特に激しい頭痛、意識障害、呂律が回らない、体や知覚の麻痺を伴う場合は、耳鼻咽喉科よりは脳神経内科、脳神経外科など、中枢性疾患の診断治療ができる専門家や、救急対応ができる施設を受診するべきです。
えびす耳鼻科いせはら耳鼻咽喉科・頭頸部外科では、耳性めまいの診断と治療を実施しています。耳性めまいは特徴的な発症契機や難聴などの耳の症状を伴うことが多く、耳鼻咽喉科ならではの診断法、治療法があります。
めまいの多くは
耳性めまいが原因
めまいの原因は症状だけでは判別が難しいですが、
耳性めまい、脳疾患によるもの、
その他の原因に大別されます。
耳性めまい
回転性めまいが特徴といわれます。頭を動かした際に短時間の回転性めまいが起こる良性発作性頭位めまい症や、難聴に伴うめまい発作を繰り返すメニエール病などは耳性めまいに含まれます。これらを発症した場合は、耳鼻咽喉科での診察と治療が必要になります。
脳疾患によるもの
頭痛、意識障害、呂律が回らない、手足の痺れなどの脳神経症状を伴うめまいは、脳出血、脳梗塞や脳腫瘍などが原因である可能性があります。このような症状がある場合は、迷わずに脳神経内科や脳神経外科へ受診してください。いずれも早期の診断治療が肝心です。さらに、糖尿病、高血圧、心疾患などといった、リスクの高い疾患を抱えている場合は、神経症状がないかを慎重に観察するのが望ましいです。
その他のめまい
ふわふわとした浮動性のめまいや、長期間続く慢性的なめまいを感じる方も少なくありません。耳鼻咽喉科では、このような症状がある方に対して、めまいの原因を探って診断をつけていきます。
耳鼻咽喉科領域のめまい疾患
耳鼻咽喉科領域で1番多く見られるめまい疾患は、良性発作性頭位めまい症です。当院では、以下の疾患について、問診・診察・検査を通じて鑑別し、診断と治療を行っていきます。
- 良性発作性頭位めまい症
- メニエール病
- 前庭神経炎
- めまいを伴う突発性難聴
- ハント症候群(ウイルス性顔面神経麻痺)
- 外リンパろう
- 聴神経腫瘍
- 起立性調節障害
- 真珠腫性中耳炎などによる半規管瘻孔
めまいの問診と検査
 問診はめまいの診断の最も大事な部分と言っても過言ではありません。発症の契機、前駆症状、難聴や耳鳴りなどの蝸牛症状を伴うかどうか、めまいの持続時間などにより、ある程度推測される疾患が絞れるからです。また、ストレスや頭痛、睡眠障害など、一見めまいと関係がなさそうな情報も重要で、既往歴や職業歴なども参考になります。何もしてないのに突然回ったのか、風邪をひいていた、とか、過剰なストレスにさらされていたとか、必要と思われることは根掘り葉掘り伺います。
問診はめまいの診断の最も大事な部分と言っても過言ではありません。発症の契機、前駆症状、難聴や耳鳴りなどの蝸牛症状を伴うかどうか、めまいの持続時間などにより、ある程度推測される疾患が絞れるからです。また、ストレスや頭痛、睡眠障害など、一見めまいと関係がなさそうな情報も重要で、既往歴や職業歴なども参考になります。何もしてないのに突然回ったのか、風邪をひいていた、とか、過剰なストレスにさらされていたとか、必要と思われることは根掘り葉掘り伺います。
難聴の有無は極めて重要な所見で、聴力検査は必須です。
耳性めまいは固視(指先など、特定のものをじっと見つめる)で症状が抑制される特徴があります。めまい検査の基本的なものは、フレンツェル眼鏡と呼ばれる凸レンズを備えた眼鏡を装着し、視界をぼんやりさせつつ、眼球を観察します。めまいを起こしている患者さんでは、眼振と呼ばれる眼球の動きが見られ、頭の位置を変えることで眼振の向きが変わったり、特徴的な動きを観察することができ、診断の助けになります。近年、もともと凸レンズと豆電球だったフレンツェル眼鏡は赤外線CCDカメラに進化し、眼球運動をより精細に観察することができるようになりました。
こうした検査をふまえ、診断を試みます。初回の診察で確定診断に至ることもありますが、典型的な症状、所見が揃わず、確定診断に至らないことも多くあります。
良発性発作性頭位
めまい症について
耳性めまいの中で最も頻度が高いのが良性発作性頭位めまい症です。起き上がった時や寝返りを打った時など、頭の位置を変えた時に突然発生する回転性のめまいが特徴です。周りがぐるぐる回るので驚くことが多いのですが、回転している時間自体は数十秒以内と短時間のことが多いです。
良発性発作性頭位めまい症の原因
内耳にある耳石が剥がれ落ち、三半規管に入ることで起こると考えられています。頭位を変えた時に重力によって耳石が動き、めまいを生じます。耳石の位置が安定すると数分以内にめまいは消失しますが、頭の位置を変えると再びめまいを起こします。
良発性発作性頭位
めまい症の症状
めまいの持続時間は数秒~1分程度のことが多いです。難聴などの蝸牛症状は通常伴いません。吐き気や嘔吐が同時に起こることが多く、これらは自律神経の反射によります。
- 朝起きた時
- 寝返りをうった時
- 急に首を動かした時
上記のような動きをしたことで、めまいを感じて受診される方が多いです。
良発性発作性頭位
めまい症の治療
急性期には強いめまい症状を起こし、吐き気も強く感じられることが多いため、まずは対症療法を行い、症状の軽減につとめます。めまい止め、吐き気止めを点滴で使用することもあります。強い症状は数日で軽快することが多く、ほとんどの患者さんで1週間程度で日常生活には支障がない程度には症状が軽減していきます。なんとなく残るふわふわ感も数週間の経過で改善することが多いです。
原因になっている部位により、特徴的な眼振が見られることがあり、病変部位を特定することができれば、epley法などの特異的な理学療法によって耳石の移動を促すことが治療につながりますが、急性期には対症療法を優先するため、多くの患者さんで適応できるわけではありません。理学療法には非特異的な体操もあり、自宅で簡単に取り組める運動は積極的に行っていただくのがよいです。いずれにしても、急性期の強い症状が取れた後は、安静にしておくよりは日常生活を通常通り行い、体操を併用してよく動くようにお勧めしています。
メニエール病について
めまいといえばメニエール病、というくらいには有名な病気なので、「自分はメニエール病ではないか」と思われる患者さんも多くいますが、典型的な症状、所見が揃うことはそれほど多くはありません。以前勉強のため調べた時に10万人に38人程度、という有病率の報告をなぜかやたら覚えておりますが、有病率の幅はその周辺で諸説あるようです。
メニエール病は、数十分~数時間持続する激しい回転性めまい発作を繰り返す病気です。主な症状としては、難聴、耳鳴り、耳閉感が挙げられ、ストレスや睡眠不足、過労などが発症に関与しているとされています。めまいを伴わず、低音障害型難聴を繰り返す蝸牛型メニエール病も存在します。
メニエール病の原因
内耳はリンパ液で満たされている部位です。しかし、リンパ液が増えすぎると内リンパ水腫を発症し、回転性めまい、とくに低音域の難聴、耳鳴りの症状が起こります。ストレスや睡眠不足、過労などが誘因として関係しているのではないかと考えられています。
メニエール病の症状
低音障害型感音難聴に伴う耳閉感(耳の詰まり)、耳鳴りに回転性めまいを伴います。めまいの持続時間は30分程度で、自律神経反射による吐き気や嘔吐が同時に起こることがあります。症状を反復することが特徴で、症状が軽快した後も、繰り返しめまい症状を起こし、聴力も次第に低下していくことが知られています。
メニエール病の検査
一般的なめまいの診察と同様に検査を進めます。難聴とめまいが症状の中心なので、聴力検査は必須で、赤外線CCDカメラを用いた眼振検査を行います。
メニエール病の治療
急性期には強いめまい症状を起こし、吐き気も強く感じられることが多いため、まずは対症療法を行い、症状の軽減につとめます。めまい止め、吐き気止めを点滴で使用することもあります。
メニエール病は初回発作時には「めまいを伴う急性低音障害型感音難聴」の診断になります。めまいに対する対症療法と平行して、急性感音難聴に準じたステロイド治療、ビタミン剤などの投薬を行います。また、病態である内リンパ水腫に対しては利尿剤を用いて内リンパ水腫の改善を図ります。水分バランスを整えるとされる五苓散や柴苓湯も選択肢になります。
症状が落ち着いているときには、生活改善に努めるのがよいでしょう。メニエール病はストレスと強く関連するといわれますが、現代社会ではストレスなく生活することはおよそ不可能と思います。有酸素運動をはじめとした運動療法や、水分摂取による内耳の水分調節などは、日常生活に取り入れやすい対策です。水筒を持って散歩に出かけましょう。
患者さんの中には、頭痛や睡眠時無呼吸症候群が隠れていることがありますので、慢性的に頭痛がある患者さんには頭痛の検査、治療を、いびきが強いとか、睡眠に問題がありそうな患者さんには睡眠時無呼吸の検査をお勧めすることもあります。めまいを反復すると、抑うつ状態になりがちで、心療内科や精神科的なサポートが必要な場合もあります。